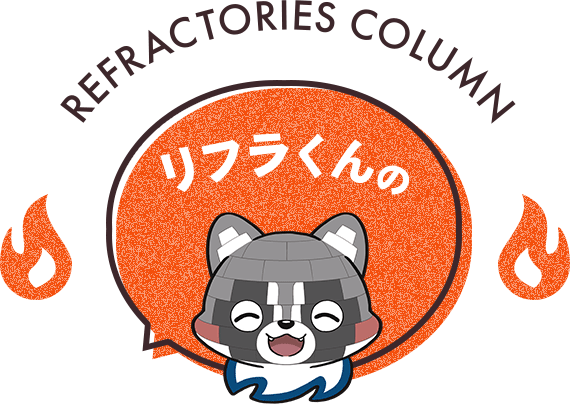日本の近代化を牽引した街・品川の歴史と品川白煉瓦の足跡を辿る

Click here for the English version
品川宿から現代まで、往来を支えた品川の街
東京都の南東部に位置する品川エリアは、交通の要衝として江戸時代から多くの人や物が行き交う場所でした。江戸(現在の東京)と京都を結ぶ幹線道路を整備するため、江戸幕府が東海道を築いた際に設けられた53カ所の宿場(休憩所)のうち、最も江戸に近い宿場町が品川宿でした。江戸の玄関口として、また当時は海に面した港町としても栄えており、人、もの、情報が全国から集まる賑やかな様子が浮世絵に描かれています。
1872年に日本初の鉄道が新橋〜横浜間で開通した際には、途中駅として品川駅が設置され、流通の拠点としての役割がさらに強まりました。また、東京湾に近いという立地から海運による物流拠点としても機能し、現在の京浜工業地帯発祥の地として、数多くの製造業が集積し、日本の近代産業を支える重要な工業地帯として発展を遂げてきました。

そんな品川の地に「品川白煉瓦製造所」が誕生したのは、1887年のことです。これは、1875年に西村勝三が創業した民間初の耐火れんが製造工場である「伊勢勝白煉瓦製造所」を、深川(現在の江東区清澄)から品川に移転したことから始まります。北品川にあった官営の品川硝子製造所の払い下げ(国有施設の民営化)を受けて工場を取得し、移転を機に名称を「品川白煉瓦製造所」と改めました。
この後、1903年に株式会社として「品川白煉瓦株式会社」を発足し、長い時を経て2009年にJFE炉材株式会社と合併し「品川リフラクトリーズ株式会社」となりました※。およそ100年にわたり、製鉄所や各種工業炉に用いられる高品質な耐火れんがを製造し続け、日本の近代化を代表する工業製品として広く知られる存在となったのです。
※品川リフラクトリーズ㈱は2025年10月に「品川リフラ㈱」と名称変更をしています。
耐火れんがから始まった品川白煉瓦のあゆみ
日本が欧米列強に肩を並べることを目指して、国家の近代化を急速に進めていた明治時代。文明開化の象徴ともいえる「ガス燈」を灯すために必要なガス発生炉用の耐火れんがを国産で賄うことを目的に、西村勝三が創業した小さな工場が品川白煉瓦の始まりです。難航する資金集めや経営難に見舞われながらも、優秀な技師たちとともに技術開発と良質な原料地の開拓に取り組み、外国産にも劣らない高品質な耐火れんがの製造に成功しました。

また、1908年には建築用れんがの事業にも進出し、1914年に開業した東京駅建設の際には建物外観を彩る化粧れんが全量を納品し、その確かな品質と優美さが高く評価されました。通称「東京駅の赤れんが」として知られるそのれんがは、今も駅舎外壁の1階、2階部分に現存しています。

年表で見る品川の発展と品川白煉瓦のあゆみ